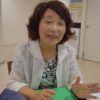ライフスタイルの変化などに伴い、この10年間で、化学物質過敏症(MCS)の患者の生活や症状などがどう変化したか、約10年前に行われた調査と比較した早稲田大学の北條祥子さんらによる論文が『International Journal of Hygiene and Environmental Health』に掲載されました。この概要についてご紹介します。論文のタイトルは「Survey on changes in subjective symptoms, onset/trigger factors, allergic diseases, and chemical exposures in the past decade of Japanese patients with multiple chemical sensitivity」。
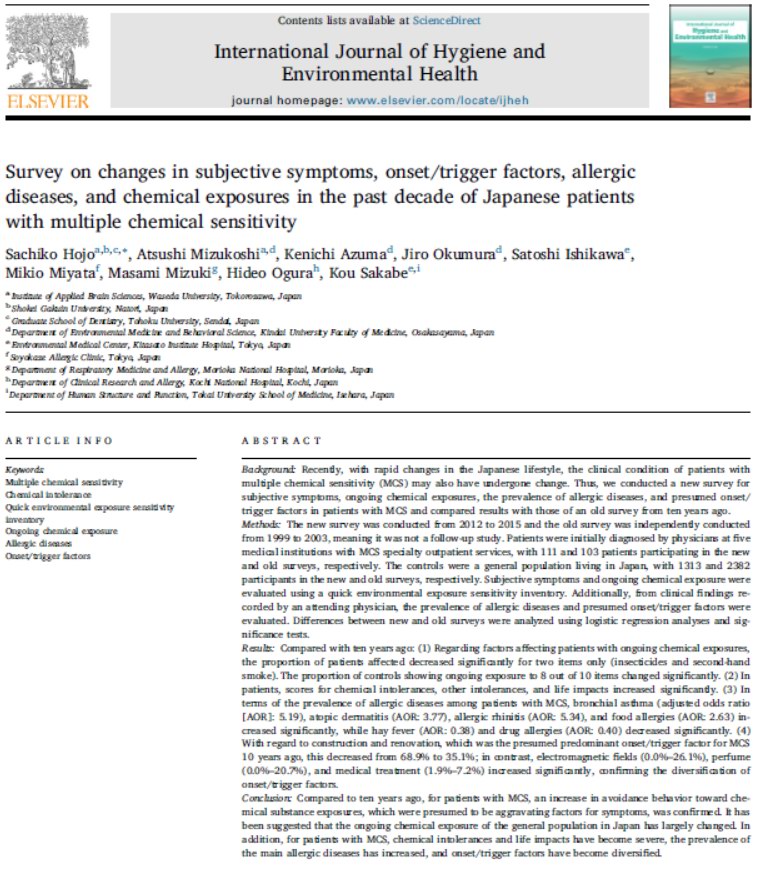
アンケートと主治医の所見記録を分析
以前の調査は1999~2003年に行われ、患者群は北里研究所病院で3人の医師が合意してMCSと診断した103人。今回新たな調査を2012~2015年に行い、患者群はそよかぜクリニック、国立病院機構盛岡病院、国立病院機構相模原病院、国立病院機構高知病院の医師がMCSと診断した111人です。今回の調査は、以前の調査のフォローアップ調査(同一対象についての調査)ではありません。
対照群は、以前の研究では2382人でした。今回は1313人で、この論文の著者らが所属する学会、研究会、大学、専門学校、建築士会、町内会、環境NPOを通して募集されました。
対象者にはQEESIと、年齢・居住県・仕事などについてのアンケートの記入を依頼。QEESIとは、MCS発症者の重症度を調べたり、またはMCSを発症者をスクリーニング(選び出す)ために米国の研究者が開発、北條さんらが日本語版を作成し、信頼性・妥当性を検証した問診票です。対照群に対しては、調査中にMCSまたはシックハウス症候群の治療を受けていたかどうかという質問項目を加えました。
患者群については、合併症、推定される発症または症状を悪化させる要因などの臨床所見記録表を主治医に作成してもらいました。
患者は失業率が増加
以上のデータについて統計学的解析を行いました。
患者群は女性が以前の調査(75.7%)、今回の調査(81.1%)ともに多数でした。
患者群の年齢は、20~39歳が以前の42.7%から今回の27.0%へと有意に減少し、40~59歳が39.8%から55.0%と有意に増加しました。
患者群の失業者は以前の7.8%から今回の29.8%へ統計学的有意に増加しました。フルタイムで働いている患者は50.0%から34.6%に有意に減少しました。逆に対照群は失業者が9.7%から6.5%へと有意に減少し、フルタイムが19.1%から40.4%と有意に増加しました。
「一般人」の日常曝露が大きく変化
日常的に曝露している微量化学物質は、患者群では以前の調査と比べて、10項目中「殺虫剤・防かび剤」「受動喫煙」の2項目でQEESI得点が有意に減少。患者が曝露を回避する行動が以前より増えていることを示唆しました。しかし、他の8項目では統計的有意な差はありませんでした。
一方で対照群については、10項目中6項目(「香水・ヘアスプレー・化粧品」「殺虫剤・防かび剤」「仕事や趣味による曝露」「燃焼したガスが部屋の中に出るガスストーブや石油ファンヒーター」「柔軟剤」「ステロイド剤・鎮痛剤・抗うつ剤・精神安定剤・睡眠薬」)が有意に増加し、2項目(「飲酒」「受動喫煙」)が有意に減少しました。この10年間で「一般人」の化学物質曝露状況が大きく変化したことが示されました。
患者の症状が重篤化
患者群の主観的症状は、今回の調査は以前と比べて「化学物質不耐性」「その他の不耐性」「日常生活障害」についてそれぞれQEESI得点が有意に増加し、患者の症状の重篤化が示唆されました。
患者のアレルギー併発が増加
MCS患者のアレルギー疾患の有病率は、今回の調査は以前と比べて、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、食物アレルギーが有意に増加しました。一方で、花粉症、薬物アレルギーは有意に減少しました。
患者の発症・悪化要因は多様化
主治医が推定した発症または症状を悪化させる要因は、以前の調査では68.9%を占めていた、家・職場・学校の新築とリフォームが、今回の調査では35.1%と際立って減少しました。これは1997年以降に13化学物質の室内空気濃度指針値が定められたことや、2003年に建築基準法が改正された成果と考えられます。
その一方で、以前は報告されなかった、電磁波(26.1%)、香料関係(20.7%)、医療関係(10.8%)が今回報告され、患者の発症・悪化要因が多様化が示されました。
MCSの発症と電磁波曝露の関係を調べるために、北條さんらが開発した電磁波過敏症のための問診票(会報102号参照)をQEESIと組み合わせて調査する必要があると、この論文は指摘しています。【網代太郎】